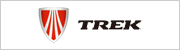Feb. 29 fri. 「話しかけても答えてくれない」
■父の死に際し、たくさんの方から弔電や花をいただき、とても感謝いたしました。ありがとうございます。通夜には、東京からわざわざ、早稲田の岡室さん、坂内さん、白水社のW君、幻冬社のTさん、桜井圭介君、そして相馬に来てもらい、霊前に線香をあげてくれた。その恩義に頭がさがる思いだったし、翌日の告別式には、ボクデスの小浜、三坂、上村、田中、そして映像の岸が来てくれた。ありがとうございました。もちろん、妹の友人や親戚、町内の隣組の方たちにもひとかたならぬ援助とご厚情をかけていただき、どう感謝の気持ちを伝えていいかわからない。そして、大工だった父のお弟子さんたちが何人も集まってくれ、いつまでも、父の話は尽きなかった。
■通夜の席といえば、酒が出るのが普通なのに、母と妹が、みんなクルマだからと、けっして酒を出さない。そういうものかと納得したが、じつはそうじゃないというのは翌日の告別式のあとに知った。お弟子さんたちが葬儀のあとは酒を飲んだが、酒を飲むと、始末におえない人たちだったのだ。通夜で酒を出していたら、みんなに迷惑をかけることになっていたと、母はわかっていたんだな。でも、通夜の夜、線香の火が消えないよう明け方までそばで見守ってくれたのは、お弟子さんの加藤さんと平野君だ。僕以上に、父との別れを惜しんでいるように見えた。自分たちで話していたのは、みんな若いときはろくでなしで、いまでいうならヤンキー一歩手前だった彼らは、父の元に働きにきてまっとうに仕事ができるよう成長したという話だ。知らなかった。息子の僕は父の仕事のこと、やっていたことのごく一部しか知らなかった。
■そして、その夜、もう遅くなってみんなが帰ったあとに、僕の小学校時代の同級生で、袋井市で市民とともに作った『月の教室』にも出演した伊地知が一番最後に来たんだ。焼香をすませたあと、「お父さんには怒られたねえ」と子ども時代の話をした。その途端だ。それまで意識的に冷静さを保っていた僕が、伊地知の顔を見、その言葉を聞いたら、つい泣きそうになった。伊地知に泣かされるとは思ってもいなかったよ。なんだろうあいつは。あんなばかやろうに泣かされるなんて、そんなおかしなことがあるだろうか。もう朝の五時過ぎぐらいだっただろうか。ようやく父と二人になれた。話しかけてももちろん返事はない。生きているあいだ人の話をちっとも聞かない人だった。やっぱり死んでも、聞いてくれないのだろうか。でも、話したかったよ、最後の最後、どうしても話したいことが山ほどあった。
■死の報せを受けたのは26日の午前2時過ぎ。すぐにクルマで静岡に帰りたかったが、仕事があったので、それをすませてから帰郷した。直前までしていたのは、「新潮」に掲載される小説の最後の直しだ。それでようやく小説が完成した。父が死んだその日に、新しい小説が完成したのもなにかの縁だったのだろうか。父は陰気なことが大嫌いだったから、できるだけ、人前ではふだん通りにふるまった。ただ、一人になるとねえ、どうしても感情が変化する。わたくしごとばかりで申し訳ない話です。でも、書いておきたかったのは、父の死を忘れないよう記録しておこうと思ったからだ。そして僕は、父が死んだことで、完全に、僕にとっての戦後が終わったと思った。戦後を死にものぐるいで生きていた人がすぐそばにいたのだ。母ももちろん、戦後を懸命に生きていたから、それを忘れているわけじゃないが、でも父の仕事ぶりがごく個人的な戦後史と重なる。思ってもみなかった。父が死ぬなんて考えたこともなかった。だって、生前、「俺は死なない」と、やはりよくわからないことを話していた父だったのだし。
(4:33 Mar. 1 2008)
Feb. 26 tue. 「父の話を」
■父が生まれたのは、一九二七年(昭和2年)の七月二七日で、芥川竜之介が死んだ数日後だったと調べてわかった。なんの関係もなかったな。芥川のことも知らないまま生きていただろう。僕の本が出たり、取材を受けた記事を読んだり、新聞で僕の書いたものをよろこんでいたというが、ほんとうに父がよろこぶことはなんだったんだろうといまになって考える。家業を継いでほしいというのは子どものころから聞かされていたし、一緒に暮らしたかったんだろうと想像するが、そんな父の思いとは異なり、僕は好き勝手なことばかりしていた。むしろそのたびに助けてくれた。子どものころのある日、母が、蝋燭にマッチで火をつけようとしていたときのことを思い出す。マッチをするがすぐに消えてしまう。いぶかりつつ、母は何度もマッチをする。だけど、なぜか火が消える。それで、ふと気がついて僕が見ると、少し離れたところから父が細長い金属パイプを口にあて、ふっと息を吹き掛け母のするマッチの火を消していたのだった。意味がわからない。いまだに意味がわからない。結局、意味がわからないままになってしまった。もっと話を聞いておくべきだった。戦争が終わった年、父は十八歳だった。その年の八月のある日、徴用されて働きに来ていた東京の工場で、これから天皇のラジオ放送があると報され、全員工場内の広場に集まるよう指示された。「また、どうせ、しっかり働いてくださいって話だろ。働きたくたって腹がへってんだこっちは。くだらねえ」と父は思い、押し入れに隠れて寝ていた。眼が覚めて外に出ると、みんなが泣いていたという。玉音放送だったよ、それ。戦争が終わっていた。日本は負けていた。押し入れの中で父は終戦を迎えてしまった。それから戦後を懸命に生きてきた。それもひとつの小さな戦後史だ。ものすごく働く人だった。だけど、聞けば若いときはでたらめだ。電柱から線を引っ張ってきて、川の水につけ、うなぎを感電死させて捕獲していたという。結局、電気泥棒、つまり「盗電」で警察に捕まった。なにをやっていたのだろう。その二、三年後に僕が生まれている。そんなでたらめな話ももっと聞いておくべきだった。もう聞くことができない。
(10:35 Feb, 26 2008)
Feb. 24 sun. 「週末は大阪へ」

■先週から週末にかけて、打ち合せ、舞台を観に行く、大阪への移動とその後の講演、京都造形芸術大学時代に教えていた学生への進路に関する相談に乗る、そしてまた東京に戻り、静岡の家からはいよいよ父親が危ないといった報せを受けるなど、いろいろあってへとへとに疲れた。
■早稲田の授業に関連して、白水社のW君、社会学の若い研究者のN君と会って、いろいろアドヴァイスをしてもらった。書籍化の方向で話が進んでいる。N君はたとえばストリートにおけるグラフィティをフィールドワークをもとに考察し、話を聞くととても刺激的だ。四月から早稲田で開講する「都市文化論」においてやはりストリートからの視点が大事だとつくづく。歩かなければな。いくつかの参照文献など教えてもらった。しっかり予習をしておかなければ。とはいっても、べつに大学の授業だからということではなく、個人的な興味の対象と授業でやろうとしている内容が重なっていることもあり、楽しみになってきた。学生にとっても刺激的な授業になればと思うのだ。
■で、金曜日の夜は、池袋へ、リージョナルシアターの一環として上演された、京都の山岡さんの作品『着座するコブ』を見る。よかった。奇妙な人間関係と、一見するとある傾向の作品のように見えて(つまり、岩松了、松田正隆的なというか)、しかし山岡さんの作品にはどこか日常から飛躍した幻想性がある。それは岸田戯曲賞の候補にもなった『静物たちの遊泳』にも感じたたが、それに興味を持っていたので、この舞台はぜひとも観ておきたかったのだ。あと田中夢が出ているという理由もあったものの、ともあれ、いくつも刺激された。観てよかった。ただ、こうした傾向の作品ばかりが評価されるのが、なんといっていいか、ある意味、制度的になっていることは危惧しており、それとはまったく異なる作品が出てこなければだめだろう。僕自身のことも含め、また異なる表現がまだ未成熟なのかもしれない。過去に戻ることではなく(八〇年代演劇にも、アングラ演劇にも後戻りしてもしょうがないし)、またべつの分脈を作ってゆかなければと、山岡さんの作品がよくできているだけに、その思いをまた新たにしたのである。
■で、その翌日(23日の土曜日)は朝、僕としては早く家を出て大阪へ移動。眠い。大阪に着く頃にはぐったりしていたものの、着いたらすぐにも「アーキフォーラム」という建築を中心に活動している人たちのセミナー(この告知はもっと早くすべきだったというか、すでに終わったわけで、いまリンクする意味がわからない)で演劇と建築をからめて話をしなければならない。こういった場合、たいてい前乗りをして体調を整えてから講演するようにしているが、今回は強行軍である。というか、その日のうちに移動と講演があると、たいてい使いものにならないのだ。それでもまあ、なんとか話をすることができた。僕がどうしてこういった場で話をすることになったか、僕自身、よく理解していなかったが、呼んでくれたY君という人が僕の舞台をよく観てくれている人だった。それがとてもうれしかったし、だからこそ、しっかり話をしようと思ったのだ。話を聞きに来てくれたのは多くが建築を学ぶ人たちらしいので、演劇の話についてどのように理解してもらえたか、建築と演劇が共有している、「構築ということ」について、もっとうまく話せればと思うが、それは今後の課題だ。
■終わってから近くの立ち飲みや的な店で懇親会。しゃべったしゃべった。ものすごくしゃべって楽しかったが、まあ、こんなことを書くのも気がひけるが、ひとり、たいへんピントが外れたことを話す人がいて、たとえば、「ポテンシャルの向う側」とかって、よく理解できない言葉を発せられ、それがちょっとね、なんかむかしの演劇人と話しているような気分になって疲れたけれど、その人が日本テレビの土屋さんに似ていることばかりが気になっていた。ホテルに戻ったらばったりと疲れて眠る。
■で、きょうチェックアウトしてすぐに東京に戻ることになっていたが、その前に、元学生だった俳優希望の人と心斎橋で会い、相談に乗る。東京に出たいと彼女は言ったが、アドバイスはできるものの、でも東京に出たからといってすべてうまくゆくわけではないし、僕にはなにも保証できない。ただ、舞台を続けることなどについて、僕が話せることはいくつかあるし、経験を話したり、東京で死にものぐるいで舞台活動をしている俳優たちの話もできる。まったく東京について実感がわいていないだろうその人に、妙な東京の幻想を与えてもしょうがない。少し、具体的な東京を知る時間を作って、それから考えればいいと思ったのだ。それが適切なアドバイスになったかわからない。いつでも相談に乗ると話して別れ、僕は新大阪へ。家に戻った。父親のことで、母から電話があった。まずいな。とてもまずいことになっている。それでもって私はいま、舞台をやっているときに等しいくらいの忙しさだ。いろいろなことが重なる。でも、死に目には会いたい。なにかあったらすぐにでもクルマで静岡に帰ろう。まだやらなくてはならない仕事は山積。新幹線の移動でとても疲れた週末だ。あと、デジカメを持って行ったのに大阪でなにも撮影できなかった。失敗。
(5:11 Feb, 25 2008)
Feb. 20 wed. 「校閲の人はすごい」


■先週の土曜日(16日)に舞台を観たとき、いまではあたりまえになっている携帯電話の電源を切ったが、それ以来、きょうまで電源を入れるのを忘れていた。「新潮」のKさんから連絡が取れないとメールがあってはじめて気がついた。ということはですね、あまり私は携帯電話を必要としていないのではないだろうか。そもそも、携帯のメールってやつをぜんぜん利用していない。アドレスさえ忘れているのだ。まあ、目覚ましと、時計のかわりかな、使うっていったら。しかしながら、やはり携帯の利用はいまや膨大になっているのだから、このサイトも携帯に向けた取り組みが必要なのではないだろうか。なにしろ、こうしてノートを書くのも、やはり遊園地再生事業団と自分自身の宣伝という目的がかなり大きいのであって、このノートを読んだ人が仕事を依頼してくれることはかなりある。あるいは、舞台そのものが、このノートと連動しているとさえ考えてもいい。だけどなあ、このノートを携帯で読むとなると、やけに長い文章を書いてしまった日はどうなんだろう。
■月曜日(18日)の深夜に東京に戻った。その翌日(19日)、小説のことで気になることがあって、また八王子に行ったのだった。それから中央線に乗ってさらに相模湖駅まで行った。相模湖まで行くのはちょっとした旅である。途中で、小仏峠があるが、電車もクルマで高速を走っても、どちらもトンネルが長い。かなりの旅である。疲れていたが行ってよかった。といった週末から、今週にかけての日々であるが、スケジュールを調べると今月から来月にかけ、大変なことになっていた。というのも、NHKの芸術劇場のために新たに撮影する必要があるからで、その撮影に立ち会い、編集やMAにも立ち会うことになったからだ。そもそも、その台本を書かなければならない。その一方で、今週末はまた大阪に行くし、来月に入ってからも、CO2が主催する映画祭の上映会と授賞式があって、また大阪だ。まったく忙しいことは幸福だ。ただ、大学の準備ができないのが、困っているところだが。
■そんなことをしているうちに、小説のゲラの直しは終わった。ゲラに鉛筆で書き込みをしてゆくのは疲れる。久しぶりにキーボードではなく、手で文章を書いたのではないか。手が痛い。書くということは、どういったことなのかと、あらためて考えることになる。でも、直しを入れ、書きこんだゲラが手元にあると、なにか達成感があるのも不思議で、コンピュータ上のテキストファイルとは異なる「作品」が生まれたようなうれしさだ。なにしろ、いろいろ手の入ったそれは、なにか汚い。その汚れに手の痕跡があるとでもいうか。ひとつ仕事を終えた。ひとつひとつ丁寧に仕事をしよう。それにしても、やはり校閲の人にはしてやられる。小説のなかで写真の描写をしている部分があるが、女が地面に腰をおろしていると思ってそう書いた。指摘されてよく見たら小さな椅子に座っていやがったよ。気がつかなかった。なぜなんだ。むかし、『牛への道』を出したときも、新潮社の校閲の人がすごかった。なぜ、こんなことを知ってるんだってことまで指摘してあった。当時の担当は、いま新潮45の編集長をしているNさんだった。Nさんに教えられたのは、校閲をしていただいた方(初老の方だったという)と廊下であった時の話だ。ちょっとちょっと、というように手招きされたので近づくと、小声で、『牛への道』が面白かったと言ってくれたという。あれだけとことん調べて、なおかつエッセイを喜んでくれたとは、なんて偉い人なんだ。まったくいちいち驚かされるのだ。
■そういえば、久しぶりに、WindowsのInternetExplorerでこのノートを開いたら、文字がぎちぎちに詰まっていた。では、FireFoxではどうかと思って確認すると、そちらは問題がない。エクスプローラーはなにかと問題が起こるのだな。考えられるのはスタイルシートだ。そう思って、少し直したら改善された。よくわからないものです。
(6:52 Feb, 21 2008)
2←「二〇〇八年二月前半」はこちら