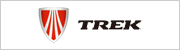May. 8 thurs. 「連休も明け、数日が経ち」 ver.2

■この年、というのはもちろん1972年の10月、アートシアター新宿文化で(その劇場の支配人だった葛井欣士郎さんが⒋月30日に亡くなられたというニュースが)ある舞台が上演された。櫻社の『ぼくらが非情の大河をくだる時』(作・清水邦夫/演出・蜷川幸雄)だ。この舞台はラスト、蟹江敬三が扮する弟を、兄の石橋蓮司が背中に背負って、客席を抜け劇場の外に出て行くという演出だった。そこに「新宿」があった。劇場の外は「新宿」という特別な街区だ。もちろん1972年、僕はまだ、静岡にいた高校生だったので見ることはできなかったが、観た人から話を聞かされたし、そのことを書いた評論やエッセイもなにかで読んだ。劇場は異様な熱気だったという。そして、劇場の外に「新宿」があった。つまりこの作品を支えているのは街である。「新宿」という街の特別な空気があったからこそ成立していたといってもいい。当時の観客はそのことを期待していたし、まだ「新宿」を信じていたにちがいない。かつてと同じような、つまり、1968年前後の、なんだかよくわからない熱に包まれた「新宿」と、アートシアター新宿文化という特別な「劇場」がひとつながりになっていると信じて疑わなかったからだ。
■その後、紀伊國屋ホールで上演されることになった(1978年)、つかこうへいの『熱海殺人事件』が文学座で初演されたのが1973年だ。これもきわめて皮肉な話というか、ことによったらそのようにして時代は変容してゆくのだろう。『ぼくらが非情の大河をくだる時』を演出した蜷川幸雄はなにかを感じていた。「新宿」の変化に気がついていた。のちに次のような文章を書いている。
あらためて読むと、大げさ過ぎるきらい、あるいはナイーブするぎると感じざるをえないが、けれど、誠実な創作者の時代感覚があると感じる。現代人劇場から、櫻社にいたるまで、政治性を帯びた作品を上演していた、清水、蜷川らが、連合赤軍事件をどう受け止めたのか。この文章だけでは正確なことはわからない。『ぼくらが非情の大河をくだる時』は事件の数ヶ月後に上演され、事件をテーマにしていることから、「重さ」を受け止めざるを得なかった。たしかに、もっと異なった反応を示した創作者は数多くいただろう。蜷川幸雄のようにナイーブに受け止めるのは、ことによったら珍しかったかもしれない。意志を持って「連合赤軍事件」を無視した者らもいたにちがいないし、それでも事件をどう乗り越えるかを課題にする「芸術」や「運動」も数多くあったはずだ。「櫻社」の旗揚げ公演は、清水邦夫の『ぽくらが非情の大河をくだる時』だった。一九七二年十月六日が初日だった。劇場はやはりアートシアター新宿文化だった。公園の中の公衆便所が舞台だった。客席には本物の樹木が運びこまれ、本物のすすきが椅子にくくりつけられた。
観客は、復活したぼくらの芝居を熱狂的に迎えてくれた。客席は若者たちで超満員だった。しかし初日の夜、観客席の一番後ろの壁に寄りかかって舞台をみていたぽくは、ぼくらの舞台が衰弱しているのを発見して、愕然としていた。
清水の戯曲も、蟹江や蓮司の演技も、そしてもちろんぼくの演出も、やせ細っていた。状況の衰退をそのまま反映した舞台は、異様に美しかったけれど、語る言葉も、演じる肉体も、すでに自己模倣を繰り返していた。
闘争と関わりをもたない若者たちが客席を埋めつくし、彼らはただゲラゲラ笑っていた。ぽくらは、現実からずれはじめていた。ぽくは、そそけだつような恐怖を味わっていた。その時にしか成りたたない演劇を、ぼくらはつくろうとしていた。その、時間に刻印された演劇が、現在の時間からずれはじめたのだ。
その夜、ぼくは清水にそのことを語った。俳優たちは、演じた肉体の火照りのなかで、上機嫌だった。ぼくと清水は、ぽくらのずれを、深刻に受けとめていた。(蜷川幸雄『千の目、千のナイフ』より)
■僕が東京に出てきたのは、1975年だった。まだその時期には、東京に来るということは、つまり、新宿に足を踏み入れることだった。かろうじて新宿という街の文化と、求心力は残っていた。アートシアター新宿文化と、それに付随する蠍座(新宿文化の地下にあった劇場)はあったが、演劇公演はなくなっていたし、そもそも、新宿文化とATGを支えていた葛井欣士郎さんが退職(74年)したあとだ。盛り場としての新宿はあった。けれどそれはもう過去の新宿とは異なる街だと知ったのはあとになってからだ。
■いま、状況劇場の上演記録を調べようとして書棚に資料を探したが見つからない(こうして、「探すより早い」とばかりに、また同じ本を買うはめになる)。ある時期、状況劇場は花園神社を追い出され、有名な新宿中央公園の「リヤカー事件」を起こしているが、1975年ごろはどこで上演していたのか(僕は東京に出た当初、映画は月に50本ほど観ていたが、演劇のことにはまったく無知だった)。あるいは、蜷川幸雄が感銘を受けた『二都物語』(1972年)はどこで上演されたかその資料が手元にないよ、だめだ、重要なのだが。
■それで書棚に資料を探しているうちに前回のノートの更新から時間が経ってしまったわけだが、ようやく手がかりを見つけたのは、『劇場へ 森秀男劇評集』(晶文社 1974年)だ。森秀男さんが1965年から、73年にかけて書いた劇評が網羅されている。小劇場もあれば、大劇場もあり、アングラもあれば新劇や商業演劇もある。この網羅ぶりがすごい。で、ともかく、状況劇場の『二都物語』の初演(おそらく蜷川が観た舞台)は、上野公園水上音楽堂で上演されている。もう新宿を離れていた。68年に撮影された『新宿泥棒日記』で唐十郎は新宿駅前で、「新宿見たけりゃいま見ておきゃれ じきに新宿、原になる」と詠む。まとめると、1968年『新宿泥棒日記』撮影。状況劇場は映画の中でも新宿花園神社でテント公演。さらに、1972年の四月から六月にかけて、唐の状況劇場は上野で『二都物語』を上演。感銘を受けた蜷川は、唐に戯曲執筆を依頼。一方、同じ年の十月、櫻社は『ぼくらが非情の大河をくだる時』をアートシアター新宿文化で公演。蜷川、ひどく落ちこむ。翌1973年6月、唐十郎作、蜷川演出で『盲導犬』を上演。さらに、10月、櫻社『泣かないのか? 泣かないのか一九七三年のために』上演。その公演を最後に櫻社は解散。あらためて蜷川さんの言葉を引用する。
どこかナルシスティックな印象を受けるものの、時代の気分が、あるいは、その時代が見事に表現されているように感じる。こうして完全に新宿が消えた。繰り返しになるが、その翌年の1974年にアートシアター新宿文化を作った葛井欣士郎さんが辞職し、劇場としてのある役割はそこで終わる。そのことは新宿の終焉を意味してはいなかったか。だから僕が75年に新宿に初めて足を踏み入れたときには、残骸だけが残っていたことになる。過去の「新宿」を探して僕は街を徘徊した。たしかにまだ暗がりはあった。怖さもあった。いかがわしさもあった。「盛り場」という言葉の、「盛り」には「性的コノテーション」があると書いたのは吉見俊哉さんだが、新宿には、もともとそうした「悪場所」としての性格があったし、じつはいまも消えてはいないだろう。だが、六〇年代の特別性はもうなかった。「サブカルチャー」「カウンターカルチャー」「ユースカルチャー」が発生する空間としては、もう時代は変化していたのではなかったか。『二都物語』をみた夜、ぼくは唐十郎にいつかぼくらに戯曲を書いて欲しいと、頼んでいた。その戯曲ができあがった。『盲導犬』という芝居だった。『盲導犬』は大成功のうちに終わった。本物の盲導犬が舞台に登場すると、劇場中に犬の匂ぃが充満した。
続いてぼくらは、『泣かないのか? 泣かないのか一九七三年のために』という芝居を上演した。清水の作品だった。残酷ショーの一座が、自分たちの過去のレパートリーを、銭湯の湯船の蓋の上で演じていくというこの芝居は、現代人劇場、櫻社と、ぽくらがやってきた演劇活動をたくみに重ね合わせていた。しかし、結果は惨憺たるものだった。ぽくは自分の才能に絶望していた。演劇的に新しいものなど、どこにもなかった。
楽の日のカーテンコールの舞台に、ぽくや清水も蟹江や蓮司と一緒に並んだ。はじめてのことだった。ぼくは超満員の観客にこう挨拶した。
「ぼくらの舞台は衰弱しています。それは無惨なくらいです。ぽくらはもう一度、ゼロからやりなおして再出発したいと思います。そして、いつか新宿へ戻ってきたいと思います。その時まで、もう新宿で芝居をやることはないでしょう。一九六九年から、一九七三年まで、本当に長い間ありがとうございました。
観客席は騒然としていた。
「早く帰ってこいよ!」
「俺たちはいつまでも待ってるぞ!」
という声が、まるで合唱のように湧きおこった。
こうして、ぽくらの新宿での演劇は終わりを告げた。ぽくらは疾走して、くたくたになって倒れこんだランナーのようなものだった。ぼくらは切実に再生したいと思っていた。アートシアターの最後の夜、舞台からひっこむとき、清水邦夫が舞台に置かれた旗竿に足をひっかけて、転びそうになった。それは象徴的な光景だった。ぽくらはよたよたして、どこか滑稽だった。ぼくらの老いは、少しずつその姿をあらわしはじめていた。(前掲書より)
■あるいは、「サブカルチャー」の質の変化もあった。
■つかこうへいの『熱海殺人事件』が1973年に文学座で公演され、それが圧倒的な支持を受けるようになってから、演劇の質が大きく変わったと書いた批評家もいたが、つかこうへいの「笑い」が持つ悪意を見抜くことができる者は数少なかった。誰にも気ずかれないまま、語られる悪意と、在日朝鮮人だったつかこうへいにとって、逃れられないテーマがその作品の背後に流れている。だが、観客の大半は(1978年から見はじめた私も含め)その悪意に気づかぬまま、無邪気に笑っていた。無邪気に笑うことが悪いことではない。しかもつかの戦略はそこにあったのだから。1978年に新宿紀伊國屋ホールに場所を移した『熱海殺人事件』は圧倒的な観客を集めた。
■72年に新宿は終わっていたが、また異なる性格の新宿がこの時期に生まれたと感じるのは、75年頃、山下洋輔に発見されたタモリが東京に頻繁に上京し新宿の「ジャックの豆の木」で芸を披露していたからだ。そして76年には東京12チャンネル(現テレビ東京)の深夜番組『空飛ぶモンティ・パイソン』が始まった。イギリスでの放送から七年遅れての放送だ。77年、赤塚不二夫を中心に「面白グループ」が誕生、79年、映画『下落合焼き鳥ムービー』(監督山本晋也)が公開されたが、私見では、まったくの失敗作。後半、ブレイク・エドワーズの傑作喜劇映画『パーティー』と同じようなギャグをタモリに演じさせたが、これがまったくなってなかった。この2本の映画を比較すると、タモリさんという人の笑いの性格もわかるのではないか。
■こうして、「新宿」のみならず、「時代の気分」が変わった。蜷川はそれを憎悪していただろう。演劇の衰弱をそうした状況に感じていたにちがいない。ではそのことがなぜ、1974年の日生劇場における東宝の舞台『ロミオとジュリエット』(つまり商業演劇)の演出になったのだろう。本人の弁によれば何度も断っているという。それを決断させたのは、「新宿」とまったく縁を切ろうとしたからではないか。そして「新宿」はあらためて、蜷川、清水らを迎えいれるような街にはならなかった。ある特別な時期の、ある特別な文化が出現したからこそ、櫻社の演劇が生まれ、一時期の状況劇場が生まれ、アートシアター新宿文化や蠍座、さらに映画に目を転じれば佐藤重臣が支配人をしていた、「黙壺子フィルム・アーカイブ」のような場所があったのだ。まだ篝火はあった。小さな自主上演の映画館はあった。その頃、僕はそうした劇場のひとつで、大半の「マルクスブラザーズ」を観た記憶がある。字幕もないままのフィルムで。
■だから、早足で書いてきたが、「新宿」は1972年に消えたのです。


■さて、もう一週間近く過ぎてしまったが、連休だからといって旅行に行くこともなく、ただ黙々と仕事をしていたものの、以前から約束していた、かつての教え子でもう卒業したが音楽を作っているS(便宜上「教え子S」とします)と、古くからの知人で大瀧詠一さんの親族でもあるS(便宜上「古くからの知人S」とします)を、5月6日に引き合わせた。で、後者のSにもらった新しくできたという名刺を見たら、ナイアガラの、あのロゴの入ったとてもきれいなデザインだった。表面には大瀧ファンにはおなじみのあの滝の絵柄。そしてロゴが美しい。これからは大瀧さんの権利関係の管理をするのだろうか(詳しく聞かなかったので推測でしかありません。申し訳ない)。会わせたかったのだ、この二人を。なにしろ教え子Sの音楽の知識は半端ない。なんでも知っている。古い話についてくる。フィル・スペクターの話だってよくわかっている。ウォールサウンドの話が出てくればすぐに話をさらに深める。細かい噂話のような話題もある程度は知っている。なんでも読んでるぞ、こいつ。途中まで、僕もついていけたが、たとえばスタジオ所属のエンジニアの人たちが作る音の性格の話などはもう専門的すぎるよ。
■だけど面白かった。会わせてよかった。僕も聞いていて、大瀧さん関係の話でいろいろなことがわかった。なかでも、古い知人Sがしてくれた1976年問題はいろいろ示唆されることが多かった。この年、大瀧さんは、『GO! GO! NIAGARA』を発売していると言われ、あ、そうだったと、これは1976年を考えるのに大事なポイントが増えたと思ったわけだ。というのも、また話が長くなりますが、この年、荒井由美が『14番目の月』を松任谷正隆のプロデュースで発表している。参加ミュージシャンの一人に細野晴臣さんがいらっしゃる。さらに、高田渡が『FISHI'G ON SUNDAY』というアルバムを細野さんのプロデュースで出す。そして大瀧さんは『GO! GO! NIAGARA』をリリース。だが、ここで大瀧さんのアルバムが一部で評価が低かったのには理由があり、同じ年に、山下達郎さんが、アメリカ録音の『CIRCUS TOWN』を出して、この二枚の音楽性を比較されたからだ。というのが、古くからの知人Sの意見。そして私は、この年、ボブ・ディランの『欲望』を買っていた。
■なるほど。大瀧さんを中心として考えるとき、さまざまなことがその時代に起きているように感じる。そして日本のポップミュージックにおいてもひとつの特別な年になっていないか。ここから考える余地がまだあると予感する。なにかが出てくると。変化は必ずあった。セックス・ピストルズはライブ活動を開始しているし、一方、ニューヨークではラモーンズがアルバムを発表。そして、1977年だ。ピストルズが『勝手にしやがれ!』を発表。パンクは、音楽の潮流にも、ファッションにも、デザインにも、さまざまな領域に大きな影響を与えた。私は病気といくつかの問題を抱え、1977年の一年間、大学を休学している。
(19:03 May. 9 2014)
May. 1 thurs. 「夏に向けての準備」 ver.2



■というわけで、今週は「とある打ち合せ」が2本。そのうちの1本は八月の、ある重要なプロジェクトについて。この国における「戦後サブカルチャー史」を考えるための仕事だが、では、それが将来的に私になにかもたらすかというと、そんなに大げさなことではないと思うものの、その仕事を通じて考えることの面白さが確実にある。面白いことをする。面白くなければやりたくない。大学で「サブカルチャー論」を担当したのは、私が希望したというより、先にそのような授業が用意されており、授業を割り振ってくれる側が私に合わせて作ってくれたのだと思う。とはいえ、これは私にとって大きな意味があった。「サブカルチャー」の概念も曖昧で、むしろゼロから考えなければいけなかったが、それがとても興味深かったからだ。授業の準備をするのが面白くてしょうがなかった。
■暗中模索だったとはいえ、とりあえず1950年代のアメリカが出発点になると考えた。というのも、ビートニクという運動があったからだ。アレン・ギンズバーグ、ウィリアム・バロウズ、ジャック・ケルアックの三人が起点。後年、『ビートニク』という映画のなかでインタビューに応えたギンズバーグが「marginal culture」という言葉で、「黒人文化」「ゲイカルチャー」「ドラッグカルチャー」などを表現しているのが印象深く、つまりそれは、「周縁」のことになるのだと考えると、「サブカルチャー」がまた異なる光彩を帯びるように感じた(サブカルチャーの定義ももっと奥行きが出る)。しばしば、一九五〇年代のことは「フィフティーズ」の言葉で表現され、「アメ車」や「リーゼント」に代表されるようなファッションで語られがちだが、それだけではないのは調べればすぐわかる。では日本の一九五〇年代はどうだったのか。まず朝鮮戦争から、六〇年安保までの十年間だということ、そのあいだになにがあったかを調べれば、文化の変容のいくつかがこの時代に萌芽しているのを知ることができる。ただ、日本は貧しかった。戦勝国であるアメリカとは比べものにならない(だから戦後の西ドイツの文化がどうだったか、あるいはイタリアがどうだったかという比較に興味を感じる)。
■と書いていたら、『ヒネミの商人』を公演していた3月の後半「ビートニク映画祭」という催しが開かれていたのを知った。なんだそうだったのかよ。『ヒネミの商人』で手一杯だったんだよ。柳下毅一郎さんと、青山南さんのトークも聞きたかったよ。
■それである区切りを考えたとき、ギンズバーグの "Howl and Other Poems" (『吠えると、その他の詩』)がアメリカで刊行された1956年ではないかと考えることができる。ケルアックの "On the Road" が1957年。バロウズの "The Naked Lunch" は1959年に刊行となっており、ま、この数年がビートニクにとっての隆盛期とはいえ、1956年はさまざまな意味で重要な年だ。あるいは、プレスリーはこの年の1月にテレビに出演し「腰の動きが卑猥」という理由でひどく非難されている。ハンガリーでは政変が発生し、ソ連が軍事介入するが(いまのウクライナに似ている)、その事件をもとに日本でニューレフトが誕生する。
■55年に芥川賞を受賞した石原慎太郎の『太陽の季節』は56年に映画化される(中平康の『狂った果実』がゴダールらフランスのヌーヴェルバーグに影響を及ぼしたとも言われるが)。立て続けに、石原原作の映画が製作され、「太陽族」の名前が定着したのも1956年。その頃、三島由紀夫はボディビルをやっていた(55年に始めている。というか、ボディビルブームがあった)。少し遅れて日本ではロカビリーがブームになる(58年ごろ。ミッキー・カーチス、平尾昌晃、山下敬二郎ら)。さらに、1956年の「経済白書」は「もはや戦後ではない」と言っている。それはウソだ。まだ日本はひどく貧しかったと思うよ。そして、なにより、私が生まれている。
■まずはここからだな。で、1960年代のことを考えたとき、特に後半から「新宿」という街区が特別な意味を持つ。いまの紀伊國屋書店の建物が出来たのが1964年だからだ。紀伊國屋書店といったら、新宿のそれであり、新宿といったら紀伊國屋書店だったんだよ、ある時期まで。あ、ジャズ喫茶もあったし、映画館もあったし(アートシアター新宿文化とか)、いくつもの劇場があったわけですが(紀伊國屋ホールが果たした役割はある時期までかなり大きかった)。それで50周年の催しが紀伊國屋書店新宿店で開かれている。これはいかないとな。あの建築は前川國男の作品だという意味でも重要だ。重要に決まっている。新宿にはある種のセクシャルさがある。盛り場にはそうした性的なコノテーションが必要だと書いたのは、吉見俊哉さんだ。「盛り場」と「悪場所」については、その吉見さんの『都市のドラマトゥルギー 東京・盛り場の社会史』(河出文庫)に詳しい。だから、豊洲など新しい商業施設の並ぶ街区が面白くないのは、そうした性的なものを感じないからだ。そして、新宿もまた暗がりが消えていく。安全なことは大事だ。なによりだと思う。だが、ある時代の文化は暗がりのなかで胚胎していた。
■ところで、「大島渚」→「佐々木守」→「ウルトラマン」(*ここ、「ウルトラQ」としてあったのを訂正しました)→「怪奇大作戦」というラインも捨てがたい。つまり「脚本家佐々木守の再評価」ということだが。ただ、再評価するにしても、ものすごく仕事をしており、ばらつきも大きくてなかなかに難しい。「ウルトラセブン」(*同上)でも名作があり、さらに『お荷物小荷物』というとんでもないドラマがある一方、べつに興味をひかれないというか、再評価するべきかどうか悩む作品も多い。ただ、「佐々木守という脚本家がいた」ということを示すだけでも意味はあるにちがいない。あと、『博士の異常な愛情』『イージーライダー』のシナリオを書いたテリー・サザーンも同様(テリー・サザーンは八〇年代になって「サタデー・ナイトライブ」の脚本にも参加している)。
■佐々木守はともかく(ともかくという言い方は失礼だが)、六〇年代の後半からのある特別な文化の出現(新宿を中心に)まで、「サブカルチャー」は56年からの約10年、この国においてはどんな状況にあったのか。ビートニクは、その後、政治運動に傾き、さらにヒッピー思想へ、ニューエイジ思想へと向かってゆくが、それには必然があった。で、そこで注目したいのは、大島渚さんの映画(あるいはジャーナリスティックに語られた「松竹ヌーベルバーグ」という一連の映画の傾向)と、赤瀬川原平さんらの「ハイレッドセンター」の芸術活動だ。ハイレッドセンターはかなりふざけている。背景に、途中で中断された「読売アンデパンダン展」の存在があり、ま、「読売アンデパンダン展」のほうは無審査方針というアンデパンダンな考え方で一貫していたのだろうが、参加する画家、作家らが、どんどん前衛化していったというか、でたらめになっていったとしか言いようがない(ネオダダの人たちのでたらめさだ)。これが素晴らしい。
■そして、その10年のあいだに、1964年が存在する。サミュエル・ベケットが初めてアメリカに渡り、『フィルム』という実験映画の撮影に立ち合う。ベケットはそこで、バスター・キートンと対面する。このことの意味、そして、同じ年にビートルズが、「エド・サリバンショー」に出演し、アメリカに初登場。アメリカのポップス界が大きく変わる。大瀧詠一さんがかつて、「ニュー・ミュージック・マガジン」(現「ミュージック・マガジン」)の「ロック研究」という欄に書いた文章によれば、すでに63年にはアメリカへの進出をビートルズは準備していたと推測できるという。いずれにしろ、区切りとしての、1956年と、1964年だ。この八年間ほどの時間を探り、掘ってゆくと、さらになにかが出てくる予感がする。
■しかし、「サブカルチャー」という言葉は、すでに1930年代に学問の世界で使われていた。若年層の文化(ユースカルチャー)の様式や形体、ありようを分析するなかで使う用語だったようだが(申し訳ない、俺、研究者じゃないんでよくわからないが。調べればいいんだけど)、それがある特別な意味を持ったのが、五〇年代だというのは、私の勝手な断定だ。坂口安吾の『日本文化私観』はどうなるのかとか、カストリ雑誌はどうなのかとか、いろいろ意見はあるかと思いますが、とりあえず、ギンズバーグが邦題『吠える』という詩集を本国で出したのが、1956年で、私が生まれたのがその年だったんだから、それでいいじゃないか。だから俺は、サブカルチャーと年齢が同じなんだよ。ニューレフトとも同じだけど。
■さて、それが「サブカル」になる時代がやってくる。そう略して使われたのは、1991年だ。だから、あれだなあ、早稲田で「サブカルチャー論」をやっていたときの学生がその頃に生まれており、彼らはほぼ「サブカル」と同年齢だ。ぐるっと巡ったのだ。そして、「サブカルチャー論」という授業を受けるときの彼らの言葉の受け止め方は、私が考えていることとはまったく異なる。というか、「サブカルチャー」という言葉を使う意味が人によってまったくちがうが、ま、そんなもんだよな、「言語」というものは。それでまあ、話をしないとどうにも通じない。この交通のために、考える必要があるようにも思う。だから誰がなんと言おうと、サブカルチャーの出発は、1956年のアメリカなんだということを説得するために考える。それが面白くてしょうがない。
■では、「新宿」が終わるのはいつか。1972年です。なぜか。以下、次号につづく。
(8:54 May. 4 2014)
4←「2014年4月後半」はこちら